福井では鯖のへしこ、と呼ばれる郷土料理が有名です。
へしことは、鯖などの青魚を塩漬けの後にぬか漬けにして発酵させた食品のことで、珍味として広く知られています。特に酒の肴として有名ですね。
今回はへしこについて詳しくお伝えしていきます。
福井のへしことは

画像引用元:https://www.heshiko.com/heshiko/
へしことは青魚を塩漬けの後にぬか漬けにして発酵させた食品です。
北海道ではさんまのぬか漬けが有名ですが、なぜ福井では鯖を用いるのかというと、それは福井が鯖街道の起点であることが由来しています。鯖街道とは福井と京都をつなぐ街道のことで、主に魚介類、鯖などを多く運ぶことが多かったので近年鯖街道と呼ばれるようになりました。
鯖は足の早い魚と言われています。つまり、傷みやすいのですね。
そんな鯖が傷んでしまわないよう、塩やぬかで漬けて加工してから運ぶ技術が開発されました。それが福井の鯖のへしこ誕生の由来となっています。
【へしこの語源】
へしこ、という名前の語源には諸説があります。漁師が魚を樽に押し込むことを「へし込む」と言ったことから生まれたという説や、塩漬けをする際ににじみ出てくる水分を「干潮(ひしお)」と呼んでおり、その言葉が訛った説などが伝えられています。
鯖のへしこの作り方
鯖のへしこは、新鮮は鯖を開いて内臓を取り除いてから塩漬けにします。その後ぬかにつけ、発酵させます。
発酵期間は10か月から2年と作り手によって違いがありますが、その間に乳酸菌発酵が進み鯖はどんどんうまみを増していきます。
昔ながらの伝統的な作り方では塩とぬかのみを使用していましたが、近年では塩漬けの後独自の調味料につけてからぬか漬けに移る製造方法もあります。
各製造業者により味付けが変わるので、いろいろと試す楽しみもありますね。
へしこの食べ方
へしこの食べ方にはいくつか種類があります。
・へしこの刺身

へしこをそのまま生でいただきます。へしこは塩味がかなり強いので、薄く切った大根を挟むなどしていただきます。
・焼きへしこのお茶漬け
適度な大きさに切ったへしこを軽く焼き、ご飯の上に載せてお茶をかけます。へしこは塩味も強いのですがうまみもとても強いので、お茶漬けにとても合います。
・へしこのパスタ
へしこをアンチョビのように使う方法です。塩味やうまみが強いへしこは、イタリアンなどにも合うので、メニューに取り入れているお店もあります。
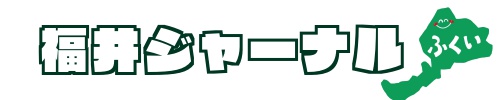



コメント